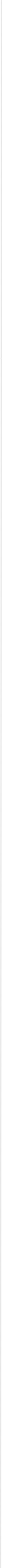Air Info 105『つまりのまがりかど- vol.2 』


2015/03/12
秋から冬、そして。
「つまりのまがりかど」と題して始めたこの投稿も初回からずいぶんと月日が経ちました。その間、今夏の芸術
祭に向けて様々な紆余曲折、転回、、があります。
それも、豪雪地の十日町市では、雪の元での長い冬の間に、作品の展開地やコンセプト、方向性が実行委員会と
共に決められ、準備されていきます。
「時の封」の展開地も松代の旧街道沿いに位置する商店街(空き家)に決まりました!
徳島に続いて商店街での展開となりました。アーケードもない、旧街道に面する古い街並が残り、個人的にも好
きな場所でもあります。又、そこでの地域活動と併せて作品展開を考え、様々な方々との関わりや連携を含め
た、松代里山で新たな地域「気流部!!」が生まれる予定となっています。実際に動き出すのは雪融け以降となるた
め、改めて「春」に詳細をお知らせ出来る事と思います。

それにしても、、十日町の雪はすごいです。街全体が埋もれています。街全体が1つの「かまくら」化している
かのような印象を持ちました。特にこの冬の積雪量は地元の人からしても少し驚く程、早く、深く積もっていっ
たそうです。(上の写真は1月中旬の大雪、松代にて)
当初は冬の植物は雪を掘り返して採取していく心積もりでした。けれど、、「掘り起こす」という雪上を俯瞰す
る感覚は、雪の降らない他所モノの視点に過ぎないのかもしれません。
人の活動そのものも雪に埋もれている訳ですから、植物含め、人もひたすら「春=雪解け」を待つ状態が「冬」
なのです。そして遅い春の訪れと共に、爆発的に成長していきます。豪雪は豪雨と異なり、土地を荒らすのでは
なく、豊かな水脈へと通じ、大地に生命を宿らせていきます。雪の下ではとんでもない豊かな土地が存在してい
るのです。そしてその土地の恵みと共に人が生きているのが妻有の里山です。

又、昨年1年間経験した個人的な里山の印象も、「移ろいゆく四季」という、良く聞く日本の里山風情ではな
く、雪解けから積雪迄、6ヶ月強の期間の植物の生命力、豊かな植生に驚かされていました。その象徴的な存在
が「紫陽花」でした。半年間、品種は異なりますが、絶え間なく彩りのある花と活き活きとした葉を見る事がで
きました。併せて雨蛙も、春先から秋まで紫陽花と共にいたりと。
下の写真は妻有の中でも秋が早く訪れる秋山郷にて、10月中旬にて撮影。


人が考える四季や季節感というものはあくまで人が考えているイメージで、植物にとってはまた違う時の流れが
存在しているのでしょう。そしてここの(妻有)の時を立ち現す「時の封」は、その植物の時の流れに同期しな
がら(人の季節感ではなく)、制作を進めていければと考えるようになりました。
冬は雪解けを待つ(雪に抗い、植物の冬の姿を求めるのではなく、雪には屈する)、その間に昨年の採取した
植物のフィルム化作業と春からの地域活動(新気流部)の準備とイメージを繰り広げる。雪の下で植物が何を感
じ、何を想うのかは不明ですが、何かその生長と作品制作をシンクロさせて考えてければと考えています。
雪解けまで、もう少しです。